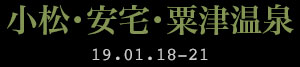
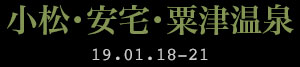

|
 |
 |
 |
|
大悲閣への石段。那谷寺の本堂です。
|
石段から見る奇岩遊仙境。洞穴の左上に願懸け猿なるものが見えます。 | 大悲閣のさらに上にある洞穴。 |
 |
 |
 |
| 大悲閣。1642年に前田利常が再建とありますが、文化庁のサイトには1597年になっています。 | 大悲閣から見下ろす境内。奥に見えるのは護摩堂。 | 大悲閣から奥へ抜ける隧道。 |
 |
 |
 |
| 境内奥にある大池。手前に堤があり、ため池のような感じです。 | 三重塔の胎蔵界大日如来。元は那谷寺根本堂の本尊で、1338年新田義貞により焼かれたとき、宗徒が運び出したもの。 | 三重塔。1642年、前田利常が建立。重文。 |
 |
 |
 |
| 楓月橋。前田利常が計画したものを、現代になって実現したとか。 | 楓月橋の木組の猿。見つけたら幸せが訪れるとか。 | 楓月橋を渡ると展望台と鎮守堂。 |
 |
 |
 |
| 展望台から見た奇岩遊仙境。 | 大悲閣唐門脇の池。奥の唐門も重文。 | 苔がきれい。奥の鳥居の向こうの堤は大池のもの。 |
 |
 |
 |
| 芭蕉句碑と翁塚。1689年に芭蕉が訪れて詠んだ句「石山の石より白し秋の風」が刻まれています。句碑は1843年、芭蕉150回忌に立てられたもの。 | 隣の翁塚には『奥の細道』の那谷寺への記述が刻まれています。これは庚申塚。縁結びの神で、粟津温泉のお末と竹松もお参りしたとか。 | 庚申塚の奥にある若宮白山神社。 |
 |
 |
 |
| 苔むした狛犬がいい感じ。 | 拝殿は1986年の新しいもの。 | 護摩堂。1649年の建築。重文。 |
 |
 |
 |
| 護摩堂。護摩を焚いて修法を行うところ。内部は金箔押しとか。 | 護摩堂。壁には唐獅子が彫られています。 | 鐘楼。1649年の建築。重文。 |
 |
 |
 |
| 参道とつなぐ道から見た鐘楼。 | 藤蔓?にも苔が生えていました。 | 出口にあった顔出し? 何でもキャラクター化すればいいというものではない気がしますが。 |