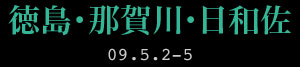
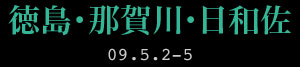

|
 |
 |
 |
|
続いて男厄坂。四十二段あります。
|
薬王寺本堂。本尊の薬師如来は1188年の大火の時に、自分で山に逃げて、自分で帰ってきて後ろ向きに入ったんで、後ろ向き薬師といわれるそうな。 | 本堂の彫刻は見事なものです。ひっきりなしに参拝客がありました。明治時代の再建。 |
 |
 |
 |
| 境内には楠の巨木が二本、枝を伸ばしていました。 | こちらは地蔵堂です。 | 随求の鐘。年の数だけ鳴らすと厄除けになるのだとか。 |
 |
 |
 |
| 霊拝堂。 | 瑜祇塔に上る厄坂。ここは男女の別はないようです。六十一段あります。 | 厄坂から見た屋根瓦。 |
 |
 |
 |
| 瑜祇塔(ゆぎとう)。1963年に作られたものですが、薬王寺のシンボルになっています。 | 瑜祇塔から見おろす日和佐の町。 | 瑜祇塔の下にもカメがいました。中は展示室になっています。 |
 |
 |
 |
| 近くからはなかなか全部は写りません。高さ約三十メートル。 | 本堂裏手にある肺太子。ここからの湧水はラジウムを含んでいて肺病に効くのだそうです。 | 日和佐川の公園になぜか立つ小便小僧。 |
 |
 |
 |
| 河原から見た薬王寺。 | 弘陽荘の離れの床はなぜか畳敷きではなくて、妙な絨毯。ここに煎餅布団を敷いて寝ました。 | 弘陽荘本館のトイレ。ウミガメがここにも。どうしてこんな怪しい照明なんでしょう。 |
 |
 |
 |
| ちょっと海から離れたところにも、古い家並が続いていました。 | これは徳島駅近くのすごい洋館。車窓から見てどうしても気になっていて、帰りに行ってみました。 | 左側のコンクリートの山みたいなものは、何なのでしょう。 |