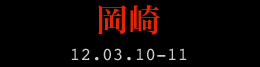
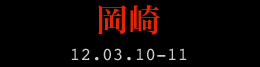

|
 |
 |
 |
|
六所神社。松平家〜徳川家が産土神として、崇拝していた神社。楼門は1688年のもの。重文。
|
六所神社拝殿。1634年のもの。重文。 | 御供所も同じころのもので重文。 |
 |
 |
 |
| 横から見た本殿、幣殿、拝殿。1634年に家光が造営したもので、重文。 | 本殿の極彩色の彫刻。 | 安心院。義経が浄瑠璃姫の菩提を弔うために建てた妙大寺というお寺が前身だとか。 |
 |
 |
 |
| 六所神社鳥居の脇の高宮神社の石碑の礎石は、義経が浄瑠璃姫の形見の麝香を埋めたという麝香塚に使われていた石だとか。 | 成就院というお寺にある浄瑠璃姫と侍女の墓。この寺も菩提を弔うために建てられたのだそうな。 | 浄瑠璃ケ淵に建つ句碑。 |
 |
 |
 |
| 姫が身を投げたという浄瑠璃ケ淵。かつては川岸の洞窟に穴観音というのが祀られていたそうですが、河川改修で消失。 | 岡崎市郷土館は元は額田郡公会堂。大正二年の洋風建築。老朽化のため、今は閉館中。 | 額田郡物産陳列所。公会堂と同じく大正二年の建築。どちらも国の重要文化財。保存修理のため、2017年まで休館。 |
 |
 |
 |
| 二十七曲がりといわれた旧東海道沿いの道案内には、金のわらじがのっていました。 | なんと書いてあったのでしょうね。最後の商という文字は読めるのですが。 | 西本願寺三河別院は、浄瑠璃姫が観月の宴に興じたというところに建っています。 |
 |
 |
 |
| 観月荘跡の石碑と侍女更科供養塔。建物の脇にひっそりと立っていました。 | 洋傘とレインコートの専門店。昔はお洒落なお店だったのでしょうね。 | 二階部分に風情が残ります。 |
 |
 |
 |
| 専福寺といお寺のちょっと変わった建物。太鼓楼なのでしょうか。ここは遊女の投げ込み寺だったとか。 | 手作り感あふれる看板の本屋さん。 | 東岡崎駅の駅ビルにて。近々建て替えられてしまうようです。 |