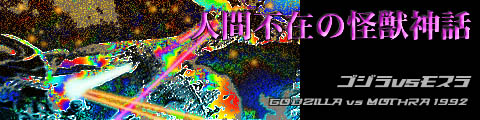
■何のためのゴジラ
『ゴジラvsキングギドラ』は観客動員300万人のヒットとなり、次回作はやはり人気のあるモスラの登場とあいなった。脚本は大森一樹だが、監督は大河原孝夫に交代、特技監督は引き続き川北紘一である。
前作でゴジラ映画と戦後日本の総括をしてしまった大森一樹にとって、モスラはともかく、もはやゴジラ映画を作り出すことは苦行に等しいものとなってしまったに相違ない。監督の交代があるにせよ、前作とのギャップはかなり激しい。
前作で明確な理由で出現したゴジラだが、ここではまた極めて存在意義の不明確な存在になっている。しかも主役は明らかにモスラとバトラであり、『ゴジラvsビオランテ』の時のように気楽に破壊に徹するというわけにもいかなくなっている。暴走する文明への警鐘という役割は新怪獣バトラが担っており、それをくい止めるモスラという役割もはっきりしているので、ゴジラはこの映画の中では極めて所在がない。文字どおり偶然通りかかると、そこにバトラやモスラがいるので、戦ってしまうという何だか情けない役所になってしまっている。
またバトラやモスラにしても、出自や存在意義が弱くて、疑問の棚上げができにくい作品になってしまった。バトラは地球生命が、自らを脅かすものを滅ぼすために生み出した怪獣ということで一応納得はできるのだが、ではモスラとはいったい何者なのであろうか?バトラとは双子(?)の関係にあるとすれば、生みの親は地球生命ということなのだろうが、何のために存在しているのかが、よくわからない。地球全体の平和と共存の象徴であるならば、バトラの果たす役割もモスラが担ってしかるべきに思えるのだが、実際には地球生命を脅かす先住民族コスモスを守って、バトラと戦っている。ゴジラ以上に存在意義が不明の怪獣となってしまったのだ。またそのコスモスという存在も、妖精的なものではなく先住民と規定してしまったが故にかえって納得しがたいものとなってしまった。
そうしたドラマ設定上の弱さに加えて、川北特撮も作りなれてきた故か、前作、前々作ほどの冴えが見られず、本編の弱さを救うまでに至っていない。特に肝心のモスラの造形に難が多く、成虫への変身シーンなど力が入っている割には、結果がいまひとつなものになってしまっている。名古屋でのリアルな実写との合成や、みなとみらい21での華麗な電磁鱗粉攻撃など、見所は随所にあるものの、パワー不足は否めない。(MM21での決戦シーンを『神を放った男』の中で、田中文雄は「原始宗教の祭礼のようだ」と評しているが、実に適切な批評であるように思う。現代においては、昔のSFのような疑似科学的理屈をつけるよりも、怪獣を神としてあつかった方がはるかにリアリティーがある)
■映像と音楽の神話世界
ところが、それでも本作は特撮の映画なのである。前二作では何とか拮抗していた本編と特撮の力関係が、この作品では明らかに特撮が本編を引っ張るまでになっている。パワーダウンの特撮が、さらにダウンした本編を何とか引っ張っているのである。大森一樹と大河原孝夫の演出力の差と言ってしまえばそれまでだが、人間よりも怪獣が文字どおりの主役となっていくこの傾向は、ゴジラ映画が40年前の第一作から、いや20年前に終わった旧シリーズから、はるかに遠い地平に来ていることを物語っているだろう。ゴジラ映画はもはや人間疎外どころではない、怪獣という神々の戦いを描く神話の世界に突入しているのかも知れない。
それを裏付けるのが、この映画での音楽の力である。伊福部昭の幻想的で神々しいとも言える旋律こそが、この映画の中で最高に説得力を持つものだった。ぎくしゃくとした人間ドラマもあらが見える特撮も、伊福部メロディーがそこに重なるとき、何十倍もの神秘的輝きを持ち観客を魅了することが出来るのだ。
本作は、記録的大ヒットをとばした。この作品で見いだされた現代の神話世界という新しいゴジラ映画像は、次の『ゴジラvsメカゴジラ』でいっそうはっきりしてくる。