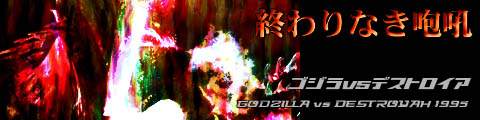
■過剰な集大成
平成ゴジラの要素を全て投入したこの作品は、良くも悪しくも巨大な集大成として、ゴジラ映画の歴史に残る、ある意味では評価を超えた記念碑的作品として見るべきだろう。
見所は無数にある。
冒頭の香港襲撃は、実景との大胆な合成というこれまでの手法を極めながら、極彩色の夜景の香港に燃えるゴジラという、刺激的な新しい「絵」を見せてくれた。
続くデストロイア出現までの人間ドラマは、実にテンポ良く過不足なく、四十年前と現在を結びつけている。単なる説明、因縁話に終わらせず、芹沢博士と伊集院、山根恵美子とゆかり、健吉という、大森一樹お得意の対になる人間関係を軸にして、単なる過去へのオマージュではなく、あくまで現在を描くという姿勢をつらぬいているのは、さすがである。
ついにデストロイア出現!水族館のシーンといい特殊部隊との闘いといいゆかりが襲われるシーンといい、これまでのゴジラ映画にはない緊迫感と恐怖感があって、楽しめる。洋画のクリーチャー的感覚もあるデストロイア幼体も「怪獣」の代表たるゴジラとの対比という点で実に良く考えられている。夕闇の中、かさこそという音ともに突然出現するデストロイアは、実に不気味。
スーパーX3のカッコ良さには、涙がにじむ。無骨さとスマートさが同居する絶妙なデザイン、「奴しかいない」という麻生指令の台詞に十分見合う黒木特佐の存在感、冷凍砲というありそうでなかった新兵器、モーフィングするゴジラの顔が一瞬ネコみたいでかわいいのもご愛敬。
御前崎でのジュニア登場シーンでは、私の同行者はハンカチで目頭を押さえていた。『vsメカゴジラ』から成長(?)を見続けていた者には「こんなに大きくなって」と、久しく会えなかった我が子の成長を見るようで、ほとんど全編緊張状態のこの映画の中で、数少ないほっとできるシーン。ジュニアのデザイン、造形も、ゴジラザウルス、ベビー、リトルの要素を無理なく消化した素晴らしいものだったと思う。
クリーンセンターでの自衛隊対デストロイアは、動く実写とミニチュア、実景との大胆な合成がうまくはまって、効果を上げている。ずらり並んだメーサー部隊は圧巻というほかない。メーサー車乗員の、緊迫感あふれる演技も印象的。降りしきる雨は、『vsビオランテ』の若狭の場面の再現か、はたまた冷凍兵器の一斉使用が原因なのかなどと、考えるのも楽しいものだ。集合体出現シーンでは、暗雲たれ込める中での、集合体のスーツ(?)の質感に目を奪われる。
ジュニアを囮に使うことの決断を三枝未希が迫られる場面は、重要場面。『vsメカゴジラ』での「ゴジラの論理」の勝利、『vsスペースゴジラ』での安易な共生幻想を、大森一樹はここで決定的に打ち砕いて振り出しに戻している。ここは、やはり小高恵美の演技が絶品。
いよいよジュニア対デストロイアだが、ここでは壮絶な怪獣同士の肉弾戦が見物。デストロイアの口がジュニアの胸をつらぬく場面では、思わず「あっ!」という声が出てしまう。健気に戦うジュニアと悪意のかたまりのようなデストロイアの対比がよく描かれていたと思う。
羽田での再会、確かにジュニアのモデルの動きのぎごちなさは多少気にはなるが、そんな些細なことよりも、ここは地球上にたった二頭の同類の、お互い変わり果てた姿での再会に心を動かすべきだろう。この悲劇を招いたのは、他ならない我々人間だということを確認して。
最後の闘いに関しては、何も言うことはない。デストロイアの存在感よりも、ここはゴジラの死を描くことが何よりも重要なのだから、デストロイアの闘いぶりや、倒すのが自衛隊であろうが何であろうが、あまり意味はないのだ。完全体が吐くオキシジェン・デストロイヤー・レイが無力なのも正解だろう。平成ゴジラは人間には制御不可能の「神」なのだから、ここで人間側の思惑通りにことが運んでしまってはいけないのである。
もちろんラスト・バトルが魅力的ではないということではない。ヴァリアブル・スライサー、集合体への分離戦法等々、川北特撮の真骨頂たる迫力ある映像が次々に繰り出される感覚飽和状態が、存分に楽しめた。
「東京を死の街にしながら」ゴジラは死んでいく。「ものすごい放射能だ」という黒木特佐の一言と、白い闇に包まれていく映像で、絶望的でありながらも美しい、破滅と死の世界が十分に描かれていたと思う。紅蓮の炎に包まれるシミュレーション映像との対比という点からも、見事な終末の映像化だったのではないだろうか。
そして、現れるシルエットと咆吼。これは単なる安易な次作へのつなぎでは決してない。この悲劇は終わらないということの明確な表現だ。人間は自らの愚行が産みだした脅威によって、破滅に瀕し、それに救われ、なおかつこれからもその脅威を背負い続ける。東京を死の街にしたぐらいの償いではすまされない業を我々は背負い続けていくという、希望も絶望も渾然一体となった「永遠の現在」が続いていくこの時代を見事に描いて、映画は終わっている。
興行面からのきびしい要求、限られた予算と時間との闘い、不毛なマニアの暴言、その他諸々の悪条件の中で、素晴らしい「90年代のゴジラ」を造り上げてくれたスタッフ一同に、心からの感謝と賛辞を送りたいと思う。
■振り出しに戻る……
この映画もまた、他のvsシリーズ同様、対立関係を軸に物語が構成されている。「芹沢博士と伊集院博士」「山根恵美子、国友長官、麻生司令と山根健吉、小沢芽留」「麻生と黒木特佐」「三枝未希と小沢芽留」「山根ゆかりと伊集院」「小沢芽留と山根健吉」といった組み合わせで新旧世代の(あるいは同世代間での)価値観、世界観の違いがはっきりと描かれている。
発明の悪用を恐れて自ら命を絶った芹沢に対し「現在の地球のためには悪魔の手を借りなければならないときもある」と言い放ちミクロオキシゲンの研究を続ける伊集院。
「どんな理由があっても、オキシジェンデストロイヤーは使ってほしくない」という恵美子や自国の被害や面子にこだわって何も出来ない国友や麻生に対し、東京を犠牲にしてもデストロイアをゴジラにぶつけようとする健吉と芽留。
「ジュニアを囮になんてできないわ」という未希に対し、「世界に目を向けて」という芽留。
…………
こうした対立は「あらゆる戦争を否定する」「一人の命は地球全体よりも重い」といった戦後民主主義的価値観と、「必要に応じて軍事力も行使すべき」「国際貢献には血を流すことも必要」といった「普通の国・日本」論の闘いのようにも見える。また、芽留と未希の対立は、「人類中心主義」と「共生思想」の対立と見ることもできる。『vsメカゴジラ』で描かれた対立の再現のようだ。
中盤までの展開では、前者が勝利し、後者は敗北するかに見える。どんなことがあっても「悪魔の発明」は使ってほしくないという恵美子の真摯な気持ちは、地球滅亡の可能性の前には、現実的説得力を欠き、無力である。国友や麻生は、ゴジラに対してもデストロイアに対しても、ほとんど何も出来ない。ゴジラへの武力行使を封じられた麻生はただ、いらだつだけ。国友にいたっては、一学生をG対策センターに引き込むことすら、自力では出来ないのである。(誠実だけど気の弱そうな篠田三郎がはまっている。)
健吉は大義のためではなく、一人の女性への漠然とした個人的想いから、結果的には世界を救う闘いに入っていく。ここら辺は、お仕事感覚でクールにゴジラと向かい合う芽留とは違っていて、おもしろい。古い男と女の役割イメージからすれば、逆だろう。
そして未希は「苦渋の選択」をして、ジュニアを囮にする芽留の行動を容認ある。現実的策を持たない感情的な理想論が敗北するかに見えるのである。
しかし、そんな単純なことでは話は終わらない。未希とともにジュニア誘導に飛び立った芽留は、未希のジュニアに対する強い想いに驚き戸惑いながらも、眼前で血を流し健気に闘うジュニアに感情移入し始める。「世界のこと」を考えて、ジュニアというひとつの命を犠牲にしようとした芽留が、未希と同様の苦渋の境地に立たされていくのである。
さらに、頼みの綱のはずのデストロイアの吐くオキシジェン・デストロイヤー・レイはゴジラに効力がない。「世界のこと」を考えて、東京を犠牲にしても世界を救おうとした目論見は見事に失敗に終わる。核兵器という人間の愚行によって産み出されたゴジラを、核を上回る「悪魔の発明」により産み出されたデストロイアで倒すことは許されないことなのである。
対立する両者とも、人間の愚行の寓意たるゴジラの前に敗北してしまう。人間にはゴジラは止められないのだ。
「東京を死の街にして」ゴジラは溶けていく。四十年前、ゴジラは一人の人間の尊い犠牲によって倒されたが、人間は愚行を改めることは出来なかった。そして四十年後の今、今度は一千万都民を犠牲にして、ゴジラは死んでいくのである。人間の愚行は、自ら償わなければならない、そう言いながら。
さらにラストには、痛烈なだめ押しが用意されている。人間は自らの力でゴジラを止めることは出来なかった。そして、また最終的な破局を、自らの愚行の犠牲者であるゴジラ・ジュニアに救われるのである。何という無力!何という皮肉!ゴジラ化したジュニアが、また大いなる災厄となることは明らかである。これは永遠に終わらない重苦しい悲劇なのだ。この鉛のような重圧感、絶望感……。
唯一暴走するゴジラに効果があったのが、冷凍兵器だというのも、興味深いところである。熱くなるのではなく、冷静になること。これがこの複雑で出口の見えない今の世界で重要なことなのだろう。しかも、その冷凍兵器にもそれほど大きな効果はないのである。ゴジラを凍らせても六時間しか持たないし、メルトダウンを防げるわけでもない。問題に決着をつけることは出来ないのである。ただ、時間を稼ぎ、次善の事態にするだけ。
伊集院と山根ゆかりの掛け合いも重要だ。白黒はっきりさせようとするゆかりに対し、感情論や決め付けを否定し、複雑な問題を単純化せず複雑に考え続けようとすること、灰色であることを主張する伊集院。最後に選択されたのは、現実的な思考をする科学者であり、ロマンティストでもあり、マッド・サイエンティストでもある、伊集院の冷凍作戦であることを考えると、この映画のテーマがよくわかる。
この映画は、対立関係を軸にドラマを作りながらも、単純な二項対立を否定している。今の世界は複雑で単純化して考えることは難しいばかりか、それでは問題は解決できないのだ。『vsメカゴジラ』で示された進歩史観に対する共生思想の二元論的な勝利、『vsスペースゴジラ』での人間中心の身勝手な共生幻想と容認される力の正義、それらを打ち砕いて振り出しに戻している。すべてを相対化して、頭を冷まして考えることを求めているのである。
90年代のゴジラの掉尾を飾るのに、これ以上の作品はないと思う。
ゴジラという名前の違う映画だったアメリカ版を経て、年末には待望の新作が公開される。果たしてゴジラ映画がどうなっていくのか今の時点ではわからないが、僕がゴジラに望むものは『vsスペースゴジラ』で、大久保博士が代弁してくれている。
「破壊だよ。それがゴジラの存在意義だろう」